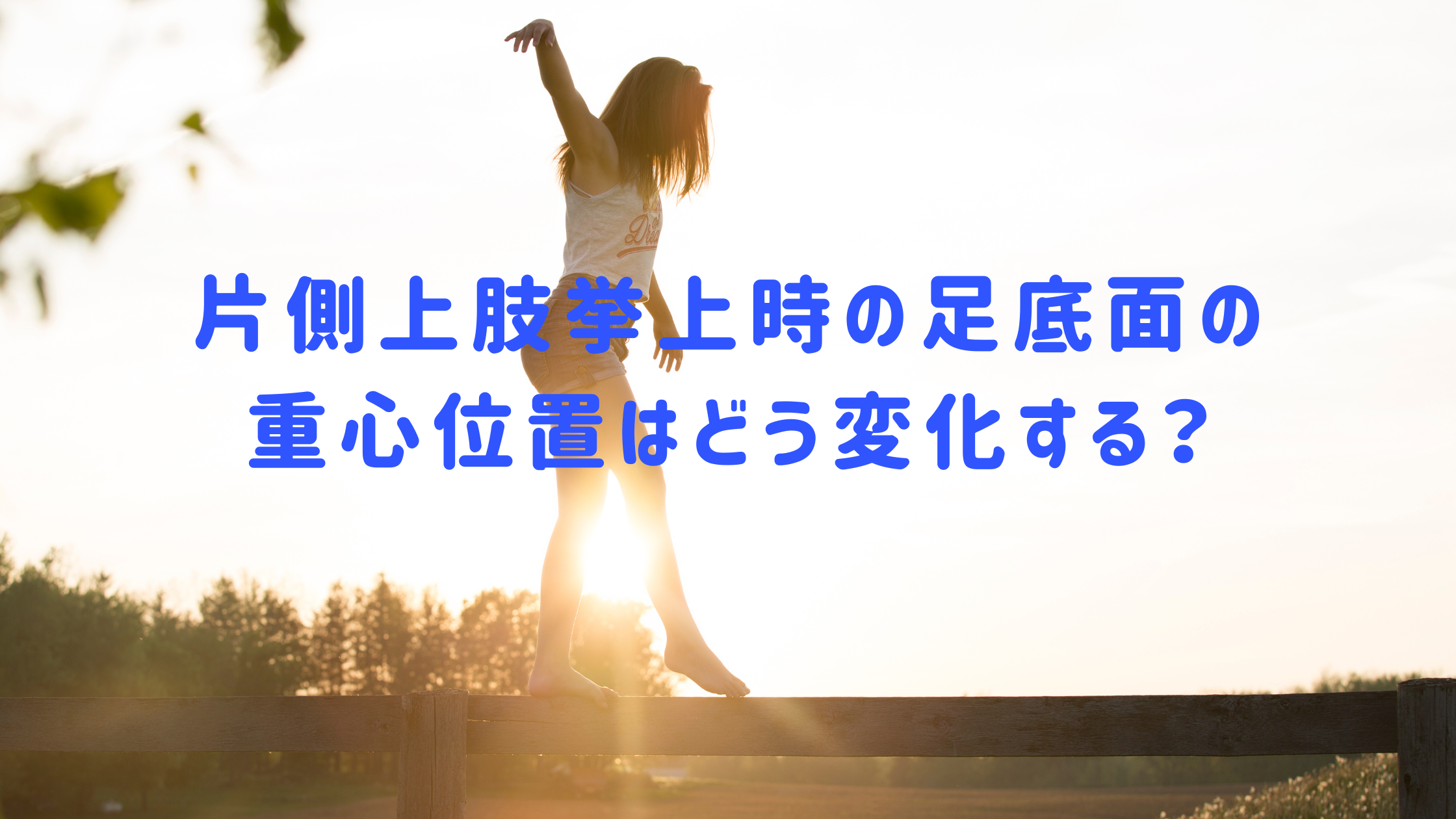はじめに
こんにちは、taiです。
本日は、臨床で良く用いる立位での上肢挙上練習を用いることがあると思いますが、その時の足底面内の重心の位置関係が健常人ではどのようになっているのかを
高木らの「健常者における上肢挙上時の姿勢制御についてー立位時の足底圧中心による検討ー」より私見も踏まえて述べていきたいと思います。詳細は是非原著をご確認ください。
内容
対象:健常男性10名
方法:
立位にて右肩屈曲保持を0°から30°毎に最大挙上まで5秒間保持を3回行い、その際の重心動揺を記録した。また、各屈曲角度で前後・左右方向への動揺平均中心変位を算出しました。
※動揺平均中心変位=本研究では立位時の上肢挙上位保持中に足底圧中心が平均的に前後、左右方向においてどのあたりの位置に存在しているのかを測定している。
結果:
0°と比較して前後方向の動揺平均中心変位は30°、60°において一様に後方変位し、90°、120°、150°、180°では前方変位と後方変位する2つの変位様式を呈しました。
左右方向の動揺平均中心変位は、30°、60°、90°で一様に右側へ変位し、120°、150°、180°では左側と右側に変位する2つの変位様式を呈しました。

健常者における上肢挙上時の姿勢制御についてー立位時の足底圧中心による検討ー
考察:
★肩屈曲角度30°、60°でみられた後方変位について
上肢挙上位に伴い、90°を最大として身体重心は前方に変位し、その前方への重心偏位を制御する為に後方にCOPを位置させたと推測。※カウンタームーブメントによる重心位置の制動と類似
以前の記事参照:☝カウンターウェイト?カウンターアクティビィティー?カウンタームーブメント?
★肩屈曲角度30°、60°、90°でみられた右側への変位について
本研究における立位姿勢の足幅は肩幅であり、左右方向への安定性が保たれており、右側へのCOPの変位が生じても姿勢が不安定となりにくい環境であったと推測。
他の研究では、上肢挙上保持により挙上側と反対側に変位するという報告もあるが、その理由として測定時の足幅が閉脚位であり構造上、不安定であった可能性があり。
★前後方向の動揺平均中心変位が90°、120°、150°、180°、左右の動揺平均中心変位が120°、150°、180°の屈曲保持において2つの変位様式を呈した点について
上肢挙上角度による身体の不安定性に対する姿勢制御の戦略には個人差がある可能性あり。
また、肩屈曲90°以上では肩甲骨を含む体幹の動きの関与が大きくなり、身体のアライメントに与える姿勢保持様式の影響が大きいことが考えられた。


カパンジー機能解剖学を参考に作成
まとめ

いかがだったでしょうか?本日は、片手挙上時における立位での足底圧中心について述べました。90°位までは一様な足底圧ですが脳卒中者では上記のようにならない可能背があり評価が必要かと思われます。また、肩屈曲120°以上では、健常者でも個人差が出やすい為、高齢者では更に実施困難であったり、代償を行ったりしている場合が多いかと思います。その際は、肩だけでなく体幹機能にも着目すると良いかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。